2024年12月5日
預金の0.4%しか守られない現実
ペイオフ制度(銀行破綻時に1000万円未満の預金が保護される制度)について、政府の話を信用していいのか否か。今日はこの検証を行います。
最初に、ペイオフの制度の概要を記しましょう。銀行が破綻した場合の預金保護についてです。
➊1000万円未満の預金は保護されます。もし5行に預金口座がある場合は5000万円まで保護されます。
❷当座預金(法人向け)と決済性の預金(個人向け)については、1000万円という上限はなく、金額の大小を問わず、全額保護されます。
実例について話すと、2010年9月に日本振興銀行が破たんしました。ルール通りに、1000万円未満の預金は全額保護され、1000万円以上の預金者は、銀行からの収奪を受けました。39%の収奪でした。
わかりやすく言うと、1億1000万円の預金があった人は1000万円までが無事でした。残りの1億円のうち39%万円が収奪されました。収奪された金額は3900万円です。収奪されなかった6100万円とペイオフの1000万円と合わせて7100万円が手元に戻ってきました。
話を戻しましょう。
本当に預金が保護されるのでしょうか?それは次の表を見れば明らかです。
日本の総預金 1,474兆円
保険対象の預金 1,337兆円
預金保険機構の資本金 5.5兆円
カバー率 0.4%
日本の総預金が1474兆円である中で、保険対象となっている預金が1337兆円あります。預金保険機構の資本金が5.5兆円ですから、割合を計算すると0.4%になります。
この数字から言えることは、日本の銀行の全てが同時に破たんした場合、カバーされるのは0.4%ということになります。つまり、全員が1000万円ずつの預金を持っていた場合、保証されるのはたったの4万円にすぎないということになってしまいます。996万円が保証の対象から外れます。
皆さんは「0.4%が現実であると」いうことを頭に入れておく必要があります。
ペイオフがインフレのきっかけを作る
話はまだ続きます。0.4%の保護では、「ペイオフはインチキだ。話が違うではないか」と人々が言い出し、暴動に発展する可能性があります。それを避けるために、政府は1337兆円の全額(もしくは過半)を保護するという行動に出るかもしれません。
具体的に言えば、預金保険機構の資本金を1337兆円にまで引き上げるか、もしくは、預金保険機構に対して1337兆円の貸し付けを行うかをするということです。それにより、預金保険機構は潤沢な現金を用意することができるので、国内全ての預金を保護することが可能になります。
ところが、政府にはこれだけ巨額のお金があるわけではありません。毎年の予算規模は100兆円超に過ぎません。その10倍以上の金額を預金保険機構に出すことは、普通の状況下では、全くできないでしょう。
ところが、非常事態になれば政府は何でもやります。1337兆円の国債を新規発行し、それを日銀に全額引き取らせます。日銀は預金保険機構に貸し出し(または増資させ)、1000万円までの預金を全額保護します。
こうすれば、「めでたし。めでたし」のはずです。ところが、ここには大きな問題があります。返済の見込みもない、空前絶後の債券発行に対して、市場は大混乱となるでしょう。
つまり、投資家がおそらく日本国債を一斉に売ることになるでしょう。投資家の心理がわかれば、このことは容易に理解できます。投資家は自分のお金が減ることが嫌なので、いつでも“びくびく“しているといっていいでしょう。危ういニュースが出た場合、「とにかく(我先に)売る」のです。財産がかかっているので、理屈を考えている余裕はありません。
債券暴落となれば、金利が大きく上がります。欧州経済危機時のギリシャのように、金利(=インフレ)が30%を超えるかもしれません。その場合、1000万円あった預金の価値は事実上30%減額されることになります。
そんな状況が何年か続けば、預金の価値は半分以下になるでしょう。この話を端的に言うならば、「政府が1000万円の預金を保護する」というのは、建前の話であり、実質は、「私達庶民が、インフレを通じて、銀行や政府の負債を肩代わりする」ということなのではないでしょうか?
「自分のお金は自分で守るしかない」ということがわかるでしょう。
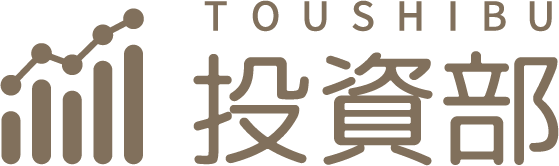

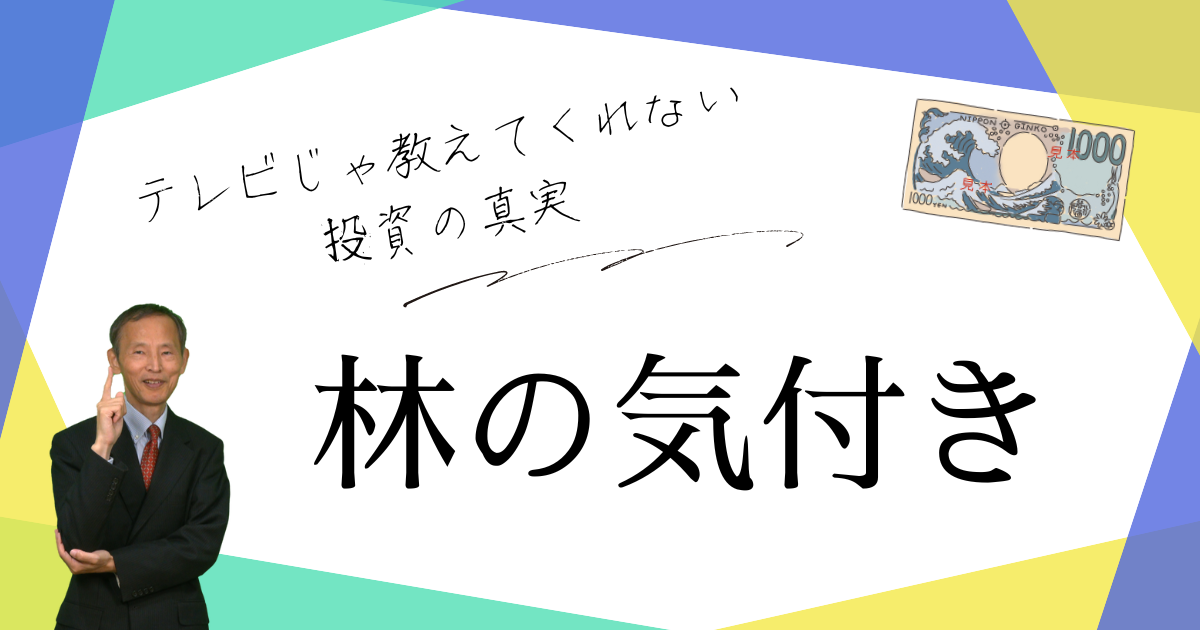
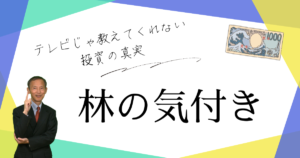
コメント
コメント一覧 (11件)
銀行破綻!狐につままれたようなお話ですが、汗水垂らして稼いだ虎の子の預金、これが政府に徴収されるということですね。
確か、政府はいざとなれば銀行破綻を起こさせる!という手法を行使することがあると以前伺ったような気がいたします。
備えあれば憂いなし、これから株式相場に浮かれることなく粛々と準備いたします。
僕が投資部を立ち上げた最大の理由は、
私たち庶民が政府からお金を巻き上げられるようなことがないようにするためです。
第二次大戦の時は、政府は私たち庶民の命を取り上げましたが
今回は財産を取り上げることが必死になってくるでしょう。
政府とは、いつの時代でも人民をいいように扱う存在です。
協力し合って難局を切り抜けていきましょう。
タンス預金も銀行預金も、インフレか財産税か何かの強制徴収で、目減りか減額されますね!
やはり、インフレに強く、かつ、カウンターパーティリスクの無い金地金を、自宅で保管が最適解でしょうか!
石岡様のおっしゃる通りだと思います。
地金のもっともいいところは、
実際に自分が地金を保管しているかどうかが誰にもわからないことです。
購入の履歴は地金店にありますが
その人が翌日以降、地金を他の人に渡したり、
またはなくしてしまったりすることだって考えられます。
ということで、誰も「地金をお前は持っているではないか」と問い詰めることは
できません。
ただし、問題は保管場所です。
これは自宅に保管するか、貸金庫に保管するかのどちらかとなります。
銀行の貸金庫はやや難点があるので、
倉庫会社の貸金庫の方がいいのではないかというのが僕の見解です。
以前、元日本銀行職員の河村小百合氏の「日本銀行 我が国に迫る危機」を読みました。
かなり、衝撃的な内容でした。
第二次大戦後の日本の苛烈な国内債務調整が近い将来繰り返されるのではないかと心配になるほどの現代の日本の債務状況です。
韻を踏むのではないでしょうか?
「財政破綻になったら何が起きるか」の章では、戦後、政府は、国民の預金を封鎖し預金を下ろせなくしてから、財産税を徴収する流れを取りました。
財産税の徴収対象は、預金上位一割が対象となったそうです。
一割は泣き寝入りしたそうですが、残り九割からの不満もなく社会不安を防いだそうです。 富裕層に対する妬みのガス抜きにもなり、政府に対する反発も抑えたのでしょう。
ちなみに、昨年、中国の銀行で預金が消えて、預金者が騒いだ事件が数件ありました。
その時は預金上位一割の方の預金は返されず、九割の預金者には返金されデモは鎮静化されたようです。
戻りますが、
その著書の中でも、興味深いのが、預金封鎖や財産税があると、数ヶ月前に、知り合いの大蔵省から聞いた地方の金持ちが、庭に金地金を入れた壺を埋めて隠し、納屋には掛軸など保管した。
税務署が調べに来たが、庭に埋めた金は見つからず助かった旨の記述が印象に残ってます。
ちなみに、生前、私の義理の祖母が、戦後の預金封鎖の話をたまにしてくれてました。本気にせず聞き流してしまいましたが、もっと聞いておけば良かった。
石岡様、大変重要な情報を教えて頂きまして誠にありがとうございました。心より感謝いたします。
終戦直後の財産税の話、中国での預金収奪の話はとても参考になりました。
投資部の会員の皆さん全員に読んでほしい内容です。
他の方にも、本件に関連するようなことをご存じでしたら
是非投稿してください。
会員各位
難しい内容ですが、本書はAmazonのaudible対応しておりますので、ご興味ありましたら、会員の方にも、是非ご視聴いただきたく、お願いします。
読むより簡単です。
多分、いつもやってます、Amazonの期間限定セールを利用されたら良いと思います。
預金封鎖などに備えて、頑張ってネット銀行の口座をいくつか増やして、ペイオフ制度の範囲内に収まるように、貯金を分散しているのですが…
預金保険機構の財源が0.4%分しかないとなると、もはや預金は向こう5〜6年程度の生活防衛費だけに抑えて、残りは全て金など投資するしかないと、今は思っています
ネット銀行は、通常の銀行(メガバンクや地方銀行)
に比べて、安全性が高いです。
その理由は、国債を大量に抱えているということがないからです。
預金をするなら、ネット銀行を利用するべきだと思います。