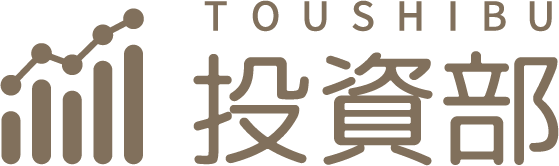- このトピックは空です。
-
投稿者投稿
-
-
匿名さん
基本的に、オルカンの年率リターン以上を元本保証等と説明している投資商品は詐欺に近いと考えられます。
AIにも基準を教えてもらいました。
皆様の参考になれば幸いです。以下、AIの回答。
投資詐欺は手口が巧妙化しており、投資初心者でも見分けられる明確な基準を持つことが重要です。以下に、詐欺案件を見分けるための明確な基準と、その理由を簡潔にまとめました。
投資詐欺を見分ける4つの明確な基準
1. 「必ず儲かる」「元本保証」と断定的な言葉を使う
o 理由: 投資には常にリスクが伴うため、絶対に利益が出ることはありえません。また、銀行預金など一部の例外を除き、元本保証を謳うことは法律で禁止されています。もしこのような言葉を使われたら、詐欺である可能性が極めて高いです。
2. 金融庁に登録されていない業者である
o 理由: 日本国内で金融商品の取引を扱うには、金融庁への登録が義務付けられています。登録されていない業者は違法であり、詐欺の温床となっています。金融庁のウェブサイトで、正規の登録業者かどうかを必ず確認しましょう。
3. 「今だけ」「あなただけ」などと、決断を急かす
o 理由: 詐欺師は、冷静に考える時間を与えないことで、相手の判断力を鈍らせようとします。本当に有利な投資案件であれば、時間をかけて検討してもらえるよう、情報提供に努めるはずです。
4. 個人名義の口座への振り込みを要求する
o 理由: 投資案件の取引は、通常、法人名義の口座で行われます。個人名義の口座への送金は、資金の追跡を困難にするための手口であり、詐欺の典型的な特徴です。
これらの基準に一つでも当てはまる場合は、安易にお金を振り込まず、消費者庁や警察などの公的機関に相談しましょう。 -
匿名さん
補足2
ポンジ・スキーム
ポンジ・スキームは、古典的な詐欺手法であるにもかかわらず、現代においても形を変えて巧妙化しています。特に巧妙な手口は、以下のような特徴を持ちます。
1. 実在するビジネスを装う
単に「高利回り」を謳うだけでなく、一見するともっともらしい事業や投資案件を偽装します。これにより、投資家は「本当に実態のあるビジネスで運用されている」と信じ込んでしまいます。
• 例1:和牛オーナー制度(安愚楽牧場事件)
o 投資家が子牛を購入し、牧場が肥育して売却、その利益を分配するというビジネスモデルでした。
o しかし、実際には契約数に対して牛の数が足りず、後から集めたお金を配当に回していました。投資家は「和牛のオーナー」という実体があるように感じていましたが、実態はポンジ・スキームでした。
• 例2:不動産投資(かぼちゃの馬車事件)
o 若者向けのシェアハウスを建設し、家賃収入をオーナーに保証するというものでした。
o こちらも、家賃保証の原資は新規のオーナーから集めたお金であり、サブリース契約(不動産会社が借り上げ、家賃を保証する契約)という健全に見える仕組みを利用した点が巧妙でした。
2. 権威や信用を利用する
詐欺師は、投資家が信頼しやすい要素を巧みに利用します。
• 有名人や専門家を広告塔にする:
o 有名人をCMに起用したり、豪華なパーティを開いたりすることで、社会的信用があるように見せかけます。有名人自身も詐欺と知らずに出演しているケースがあり、投資家は「テレビCMが放映されているから安全だ」と誤解してしまいます。
• 「劇場型」勧誘:
o カフェなどで、勧誘役、成功者役、主宰者役など複数の人物が登場し、あたかもその場で成功体験が語られているかのように見せかける手法です。場の雰囲気に流され、冷静な判断ができなくなります。
3. 紹介システムを利用した「ねずみ講」方式
• 投資家が新たな投資家を紹介すると、紹介料や手数料がもらえる仕組みを取り入れています。これにより、投資家自身が被害者であると同時に、知らず知らずのうちに加害者にもなってしまいます。
• 最初に入金された配当金で「儲かった」と信じ込んだ投資家は、さらに多くの知人や友人に勧誘を行い、スキームを拡大させていきます。このシステムは、詐欺師が直接勧誘の手間を省き、被害を急速に拡大させる最も効果的な手法の一つです。
まとめ
これらの巧妙な手口は、単に「高利回り」を謳うだけでなく、**「信頼できる実体がある」「誰もが知っている有名なものだ」「友人からの紹介だから安心だ」**といった投資家の心理的な隙を突いてきます。
投資を検討する際は、事業内容や収益の仕組みが本当に理にかなっているか、金融庁の登録があるかなど、表面的な情報だけでなく、本質的な部分を冷静に見極めることが重要です。 -
匿名さん
補足1
「銘柄釣り上げ型詐欺」について
詐欺の具体的な例として、「銘柄釣り上げ型詐欺」(Pump and Dump) があります。
概要
この詐欺は、SNSやメッセージアプリ、偽の投資グループなどを通じて行われます。詐欺師は、事前に仕込んだ特定の銘柄(多くは流動性の低い小型株)を、あたかも**「確実に上昇する」**かのように宣伝し、投資家を煽ります。
事例の具体的な流れ
1. ターゲットの選定と勧誘:
o 詐欺師は、SNSなどで投資初心者や知識の浅い人をターゲットにします。
o 「無料の投資グループ」や「特別な情報を提供するコミュニティ」などに誘い込みます。
2. 実績の偽装と信頼構築:
o 最初は、本当に上昇する銘柄(ただし、すでに詐欺師が買い付けているもの)をいくつか紹介し、的中させて見せます。
o この成功体験によって、投資家は「このグループは本物だ」「この人は本当に稼げる情報を持っている」と信じ込みます。
o この段階で、投資家は少額の投資で利益を出すことができ、さらに信頼を深めていきます。
3. 「釣り上げ」と利益の確保:
o 信頼を得た後、詐欺師は本命の銘柄を指定し、**「明日、大口の資金が入る」「この銘柄は近々大発表がある」**などと、いよいよ投資を促します。
o これまでの成功体験から、多くの投資家は疑うことなく、指定された銘柄に大金を投じます。
o 大量の買い注文が入ることで株価は急騰し、まさに「予告通り」上昇したように見えます。
4. 「投げ売り」と詐欺の完遂:
o 株価が十分に上昇したと判断したところで、詐欺師は事前に仕込んでおいた株を一斉に売却します。
o これにより、株価は暴落し、取り残された多くの投資家は多額の損失を被ります。
o 詐欺師は姿を消し、投資家は連絡が取れなくなります。
なぜ騙されてしまうのか
• 「本物」と思わせる初期の成功体験: 投資家が自ら体験した「儲かった」という事実が、冷静な判断を鈍らせる最大の要因です。
• 集団心理と FOMO(Fear of Missing Out): 「他の人も儲けている」「乗り遅れたくない」という焦りや不安が、冷静な思考を奪います。
• 情報の限定性: 「特別な情報」や「グループ内限定の情報」とすることで、投資家は自分だけが特別な機会を得ていると錯覚します。
この詐欺は、**「一度は本当に儲けさせてくれる」**という点が非常に巧妙であり、投資家が「詐欺かもしれない」と疑う隙を与えません。これが、この種の詐欺が何度も繰り返される理由です。 -
匿名さん05
林先生今晩は、つかぬ事をお尋ねします。
投資部は最近新しいラインを追加しましたか、
いきなり投資部に入りたくないですか、と誘って来たのですが最近いろんな偽物が出ているのでスルーしましたが、本物でしたか。 -
匿名TR
半年ほど前から株取引紹介で利益獲得実績(今思えば嘘の実績)をメールで送り続けられました。AIを使用しているからとの事でした。その担当者は某一流証券会社にいましたこのことで、しゃべり方も丁寧で安心出来そうでした、8月26日から9月19日迄にテンバガーを含んで5銘柄を信用買いで保有していますが、手仕舞いが案内の通り出来ません・100円以下の銘柄です。しかもその会社は来年株式上場予定と言っているけど、おかしいと思って受け付けの女性に社長の名前を聞きましたら金融庁から警告を受けてる人物でした。審査が通らないのにヌケヌケと嘘をつきますね。そしておかしいと感じたのはアイパッドをプレゼントで送りつけてきて、その後で契約書が届きます内容は内容は(ソフトウエア使用許諾書)の名称ですソフトウエアを購入したことになるわけですよね。だから法的には詐欺が成立するのは非常に難しいと思います。非常に巧妙になった手口です。この中の1銘柄はユーチューブで新型ロボットウェアーを発表するからすぐに株価上昇とのことで1週間後に(9月26日)5倍上昇での手仕舞いとの事でしたが逆に、下がりました。全銘柄移動平均線が75日線の下で乖離も相当ありますので上昇には時間が係りますので追い証が来ない内に少しずつ損切りしてこれは忘れて、少なくなった残金を投資部での運用に回す予定です。林先生の事を10日でも早く知ることが出来ていたらと思いますが、その分を必ず取り返します!82才ですがまだ現役で仕事もしていますので一生懸命頑張ってまいりますので宜しくお願いいたします。
-
匿名さん
最近、AIソフト販売契約書を締結して高額でソフトを買つた形で、銘柄紹介料金を90万(テンバガー予定あがるどころか下げ)他に4銘柄いれて会社名をネットで調査する間もないくらいに矢継ぎ早に冷静さを奪われた感じになります。5銘柄で¥2、696、000です。詐欺の手口が変わりました。最初は59、000からでした。一度付き合ったら大変です。
-
ふくさん
本スキームの倒産隔離は、どのように組成されていますか?と、私は一言聞くようにしてます。目が泳いだら、詐欺認定。
-
-
投稿者投稿